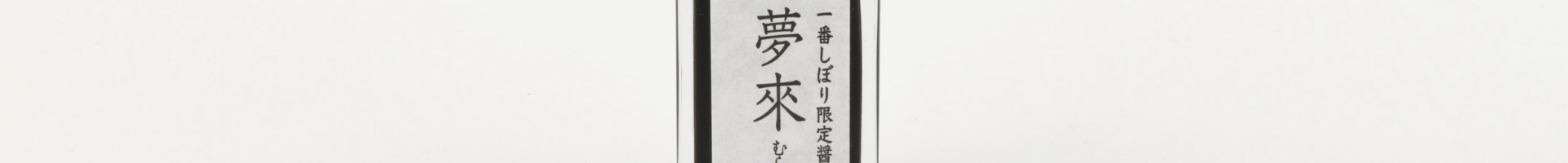
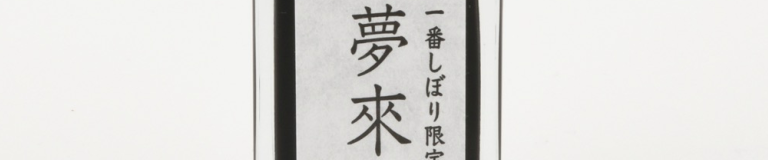
三浦家は初代・亀衛門(寶暦12年没)から現当主である三浦誠司まで九代を数えますが、長命な者が多いことが位牌過去帳からもわかります。例えば創業者村次は85歳、妻のヒサは87歳、先代杜氏・重信は93歳、その妻方子も98歳の長寿を全うしました。
古い時代の詳細は知る由もありませんが、先代杜氏に関して述べるなら、その健康の秘訣は味噌汁にあったと言っても過言ではないでしょう。健康志向が然程強いわけでもなく、愛飲家で愛煙家、おまけに甘党でもあった先代ですが、毎日の食事には欠かさず味噌汁を飲んでおりました。いりこで取った出汁に畑で採れた旬の野菜や豆腐、わかめなどを入れた季節の味噌汁を、先代は何よりも好んで食しました。人生最期の日の未明「味噌汁が飲みたい」とつぶやいた先代に、妻の方子は「もう少しして夜が明けたら作りましょうね」と言葉をかけました。そして早朝に寝室に運ばれた炊きたてのご飯とみそ汁を「ああ、美味しい」とうれしそうに食べ、その日の昼過ぎに眠るように息を引き取り、93歳の天寿を全うし大往生を遂げたのです。先代の長寿の秘訣、健康の素はまさに毎日の味噌汁であったと言えましょう。

世間では、1980年代の減塩運動あたりから「減塩」をうたった味噌や醤油、梅干しを始めとする保存食が数多く登場してきました。そして、あたかも塩分過剰摂取の原因が味噌汁や醤油にあるという誤解を与えるような情報が錯綜し、これらが消費の落ち込みを招きました。しかしながら、いかなる食材でも薬でも、上手に用いれば効を奏し、用い方を誤ればよからぬ結果を招くものではないでしょうか?例えば、塩分が高いとされる味噌も、味噌汁にする際、具材に海藻やカリウム含有率の高い野菜などを上手に用いると、余分な塩分の排出を促します。
塩分の過剰摂取は、確かに私たちの身体に良くない影響を及ぼします。しかし、元来味噌や醤油に含まれる塩分は「保存」という大切な役割を担ってきたものなのです。そしてそれは先人達が生み出した、生きるための尊い智慧であったはずです。「減塩」するなら、それを「保存」するためにはそこに塩とは違う何かを加えなければなりません。それは何か……。「減塩」という魅力的な言葉に安易にに飛びつくだけでなく、そこに潜む問題にも目を向ける必要があるのではないでしょうか?味噌や醤油が本来備えている良さ、それをよりよく引き出す工夫を取り入れて、自然の摂理に則った伝統的な製法による、安心安全な味噌や醤油を毎日の食卓に取り入れてはいかがでしょう。
和食のユネスコ無形文化遺産登録や、逆輸入の形で国内でも人気が高まったマクロビオテックの影響などもあり、我が国の伝統的な調味料である味噌・醤油の価値は見直されつつあります。私たちが先人たちから受け継いできたこの優れた調味料が持つ、本来の美味しさや素晴らしさをさらに広め、より多くの方にそれをご賞味いただきたい、それが私どもの願いでございます。
